
タトゥーとの偶然の出会いから、彫り師としての人生が始まった麻緒さん。スタジオの立ち上げ、家庭との両立、そして業界を揺るがす裁判──さまざまな経験を重ねながらも、“肌との対話”を大切に、今も彫り続けています。
唯一無二のスタイルを築き上げた彼女の歩みと、そこに込められた想いを伺いました。
タトゥーとの出会いは、偶然のインスピレーションから
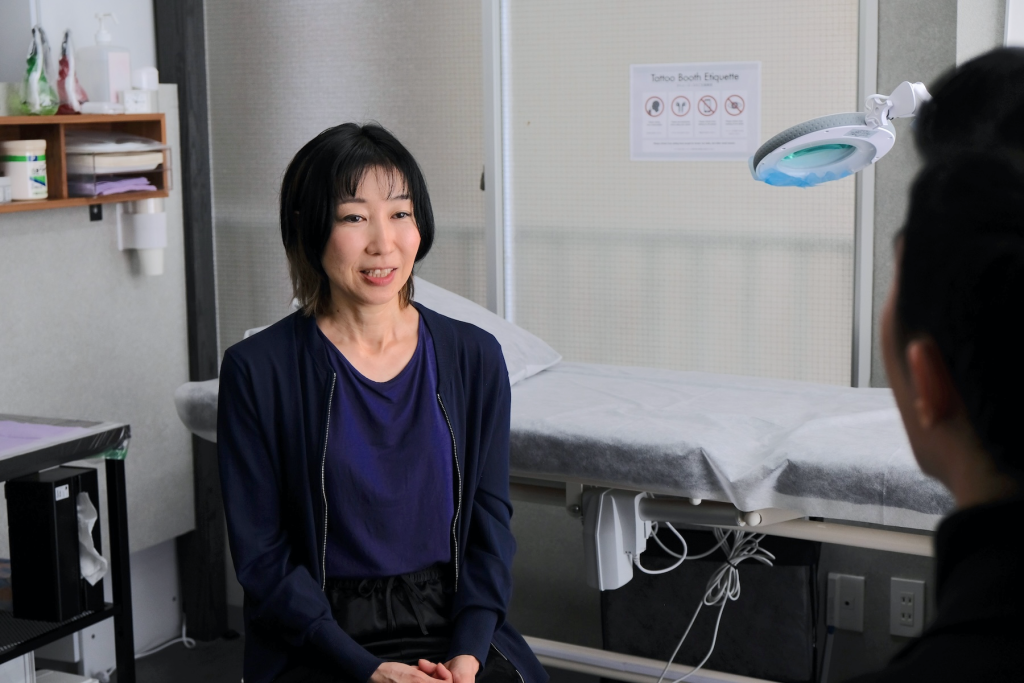
「麻緒(あさお)といいます。本名なんですけど、昔はちょっと変わってる名前って言われて。でも、インパクトもあるなと思ってます。」
アパレル業界でパタンナーとして働いていた麻緒さん。経済不況のあおりを受けて職を失った頃、飲食店でのアルバイト先で女性の足首に入っていたタトゥーが、人生の転機となった。
「それまでタトゥーは見たことはあったんですけど、特別意識はしていなくて。でもその時は『あ、次これやりたいな』って直感的に思ったんです。何も知らなかったので図書館で調べたり、本屋で雑誌を探したりして。」
彫り師としての道を選ぶ決断に、迷いはなかった。子どもの頃からものづくりが好きだった自分にとって、それは自然な選択だったという。
“自分に入れたい”より、“これを仕事にしたい”と思った

「自分に入れたいっていうより、仕事にしたいなっていう気持ちの方が先でした。」
最初に自身に入れたタトゥーは、自身の名前に由来する“麻の葉”をモチーフにした和彫り。親に言うべきか迷いつつも、「仕事にするなら小さいのじゃなくて、ある程度大きめに入れよう」と決めた。
デザインを決めたきっかけは、タトゥーマシンを握る前、「絵を持ってきてもいいよ」と言ってくれた彫り師の影響が大きいと言う。
「その彫り師の方は、ブラジルと日本のハーフで、トライバルのスタイルでした。自分のルーツを作品に反映させてるのがかっこいいと思って。私は“ただの日本人”だけど、何か自分の中にもあるんじゃないかなと。」
和彫りという日本のスタイルに惹かれつつも、完全な伝統ではなく、自分なりの表現を重ねていくことにした。
弟子入りを選ばず、独学で切り拓いた道
彫り師としての一歩は、ゆるやかな見学から始まった。
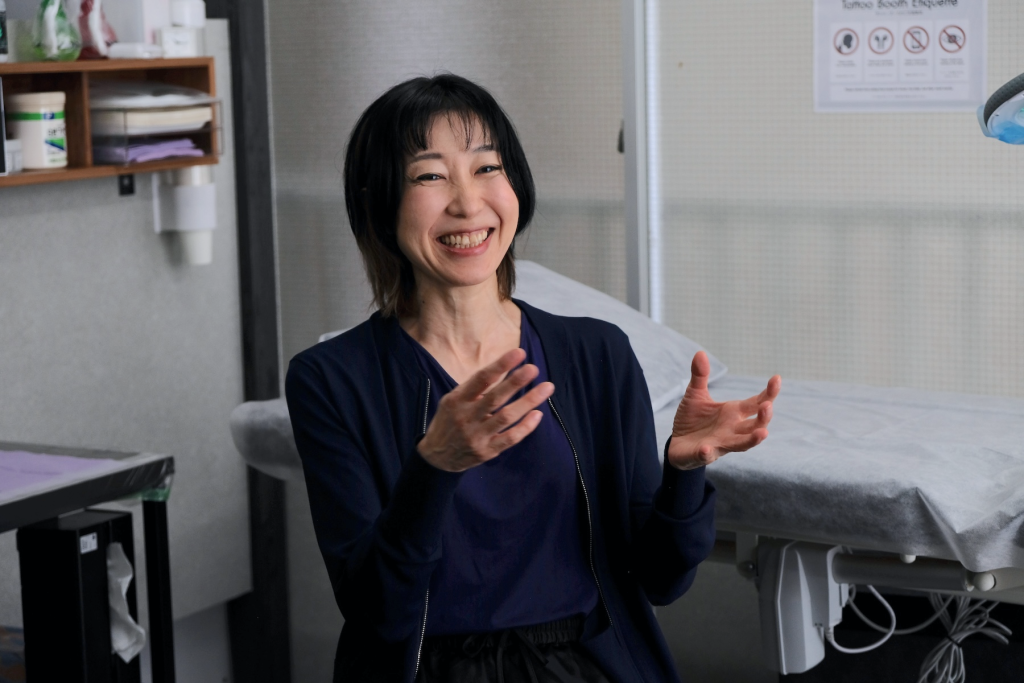
「見学に通っていたスタジオで、たまたま行商人のようにタトゥーマシンを売りに来てた人に遭遇したんです(笑)。ちょうどその頃に『そろそろマシン買ってもいいんじゃない?』って言われてて。インクも全色くださいって頼んで、そこから本格的に始めました。」
タトゥーマシンを手にしてからは、バイト先の後輩や知人たちが肌を貸してくれ、施術の経験を重ねていった。
「このスペースだったらいいよ、って場所を貸してくれる人もいたりして。別のスタジオで間借りさせてもらうこともありました。」
弟子入りは選ばなかった。最初に施術を受けたスタジオの彫り師からこう言われたのがきっかけだった。
「『一門に入るのはおすすめしないよ。入ったら抜けられないし、住み込みで上下関係も厳しいよ』って言われて。私は弟子入りしない方法で始めました。」
教わることはあっても、無料ではなかった。

「最初は『教えてほしい!』って思ってたんですけど、“授業料”って言われて。“そうか、当然だよな”って(笑)。正直、当時は高いなと思いましたけど、頑張ってバイトして通ってました。」
遠回りに思える道だったが、今振り返れば、その過程で得たものは大きかったと感じている。
プライベートスタジオから始まったスタジオ運営という選択肢
タトゥーマシンを手に入れ、実際に人に彫るようになってからも、すぐにスタジオを持ったわけではなかった。最初の施術場所は、自宅を改装したスペースだったという。
「今だったら難しいと思うんですけど、自宅を“別世界”みたいに作って、プライベートスタジオとしてスタートしました。人の出入りも増えてきて、隣の家にピンポンしちゃうとか(笑)。“これはまずいな”って思って、スタジオ探しを始めた感じです。」
本格的に現在のスタジオに移ったのは2003年。その4年ほど前からは、教わっていたタトゥースタジオや、間借りで施術を行うようになっていた。
「美容系のサロンの一角を借りて施術する時もありましたね。当時はネイルアートなどと並んで“面白いコンテンツ”としてタトゥーを取り入れてくれるサロンもあって。」
完全な所属や“弟子入り”とはまた異なる、柔軟なスタイルで経験を積みながら、麻緒さんは彫り師としての足場を固めていった。
10年ひとりで彫り続けて見えた、自分らしいスタジオのかたち
スタジオを開いた当初から、麻緒さんは“彫ること”に集中する日々を送っていた。独立後しばらくはスタッフもいない完全な一人体制。それでも、「仕事をするのが楽しすぎて、10年くらいほとんど休まず彫ってました」と笑う。
「最初は妹が手伝ってくれてたんですけど、彫るのは私ひとり。ずっと黙々と彫っていて、そこにバイトしたいって言ってくれたお客さんが来てくれたりして、少しずつスタッフが増えていきました。その人は今も一緒に働いてくれてます。」
しかし、働き続ける中で年齢を意識するようになり、「子どもが欲しい」という想いも芽生えてくる。2011年に第一子を出産。そこから、スタジオの在り方も少しずつ変化していった。
「すぐ復帰できたんですけど、今までと考え方は変わりましたね。自分中心じゃなくて、人のために生きるってこういうことなんだなって。そこから、“このままじゃダメかも”って、スタジオの仕組みもちゃんと考えるようになりました。」
家庭との両立、スタッフとの関係性、そしてお客さんとの接点。すべてにおいて、より「人」を意識した運営を意識するようになったという。
タトゥー摘発と裁判、そして“アートとしての再出発”
2015年、日本中のタトゥー業界に衝撃が走る出来事が起こる。「医師免許を持たずに施術するのは違法」とする、いわゆる“タトゥー裁判”だ。麻緒さんのスタジオも、その波を避けることはできなかった。

「看板に“TATTOO”って出してたんですけど、それも外して、“ここ何屋さん?”って思われるくらいの静かな営業に切り替えました。本当にショックで怖かったです。タトゥーを続けられなくなるんじゃないかって」
裁判では最終的に「タトゥーは医療行為ではなく、アートである」との判断が下る。麻緒さんはその判決に背中を押されるように、アートへの探究心を新たにした。
「それなら“もう一度ちゃんとアートを学びたいな”と思って、今は武蔵野美術大学の通信課程で木版画を専攻してます。一旦休学中ですが、来年から復学予定です。」
木を彫る版画と、肌を彫るタトゥー。 原理は違えど道具を使って彫るというところに通じるところも多い。先生の言葉が今も印象に残っている。
「“版画は版木との対話である”って言うんですけど、私の場合は、それが“肌との対話”だなって。」
「変化しても美しい」線を描く——肌と向き合う彫り師の美学
麻緒さんの作品には、繊細な線と大胆な構成が共存する。鶴や富士などの和モチーフをベースにしながらも、トライバルの要素や抽象的なストロークも含まれる。



「一人で長いことやってるとありがたいことにいろんなオーダーが来るので、逆にお客さんがくれたアイディアに自分の中にない発想とか発見があったりします。今は特定のジャンルというより、自分なりの自分だけができるものをやっていきたいです。」
スタイルは初期から徐々に変化してきたが、根底にあるのは“肌との対話”という姿勢だ。
「何回も来てくれてる方だとかなり分かってくるんです。発色は必ずしも肌の濃淡によらなかったり、いろいろな発見があります。やればやるほど本当に奥が深いです。」
均一な細い線を引く難しさ、部位ごとのクセ、肌質の違い──。そのすべてに対して、丁寧に、誠実に向き合う。
「タトゥーはどうしても経年変化ってあるんです。2、3年はわからなくて、その後になってから分かってくる。先を見てないと、その時に一番綺麗に見えるものを彫ってしまうと思うんですけど、長くやってると、前に彫ったタトゥーに再会するんです。」
「『その人の肌にいつもずっとあるんだな』って。年月が経って、多少褪せたり、線が太くなったり滲んだりしても、それでもまだ良いと思えるデザインにこだわってます。」
10年、15年経ったタトゥーと再会したとき、それでも美しいと思えるかどうか。その答えを見据えて、麻緒さんは一本一本の線を彫っている。
タトゥーは「真剣な楽しみ」──死ぬまで彫り続けたい
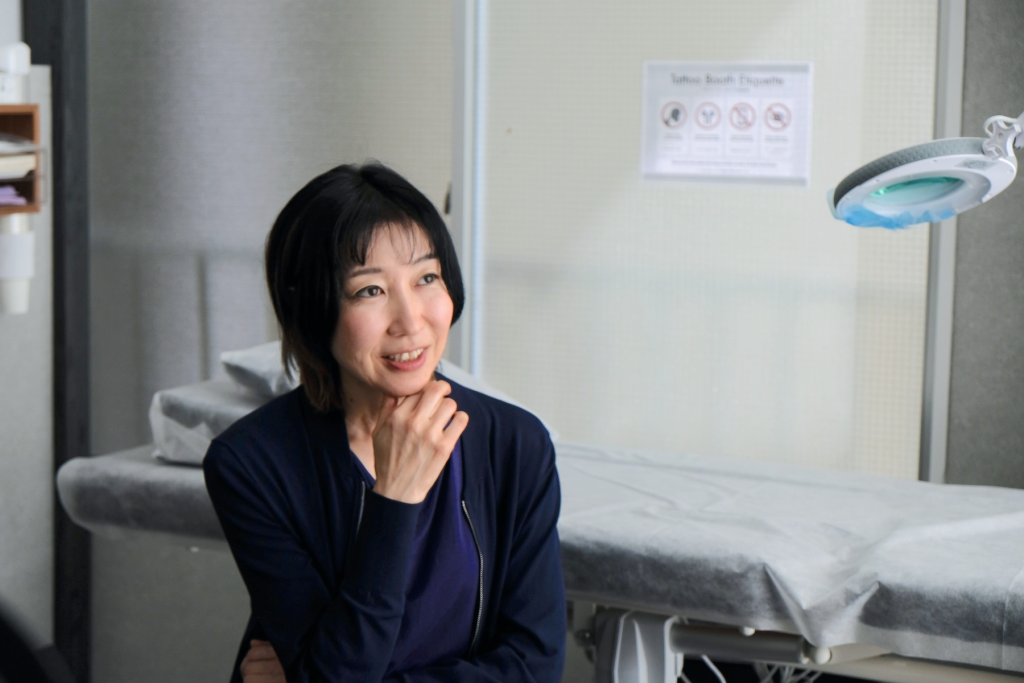
「麻緒さんにとってタトゥーとは何ですか?」という問いに対し、少し考えて、こう答えた。
「”真剣な楽しみ”です。ご飯みたいに、彫ってない日が続くと、なんだか調子が出ないというか、自分が欠けてる気がするんです。」
「人の肌に彫る感触が好きなんです。肌って伸びるし、血も出るし、痛いし、難しいんですけど、彫った後すごいスッキリするんですよね。マシーンの振動と肌にインクが入っていくときの抵抗感。彫ってる工程そのものが好きでずっと続けていきたい。そのために、良い作品を作り続けたいです。」
何十年続けても、飽きることはないという。むしろ、経験を重ねるほど、タトゥーという表現の奥深さに気づいていく。
「経営だけにしたら?って言われることもあります。でも、私にとっては彫ることそのものが必要なんです。だから、死ぬまで現役でいたいと思ってます。」
“人生を創造する”ということ──麻緒さんのミッション
麻緒さんのスタジオには、こんなミッションが掲げられている。
Realizing a cool, creative and passionate life.
クールで、創造的で、情熱的な人生を実現する。
タトゥーは、入れる側にとっても、彫る側にとっても、人生の在り方を変える“創造的な行為”だ。
「スタジオに来てくれるお客様、一緒に働く仲間にも、ただの消費じゃなくて、クリエイティブな人生を歩んでほしい。そういう場でありたいと思ってます。」
タトゥーという文化に真摯に向き合いながら、自分の道を、自分の方法で切り拓いてきた麻緒さん。その背中からは、静かで力強い信念がにじみ出ていた。





